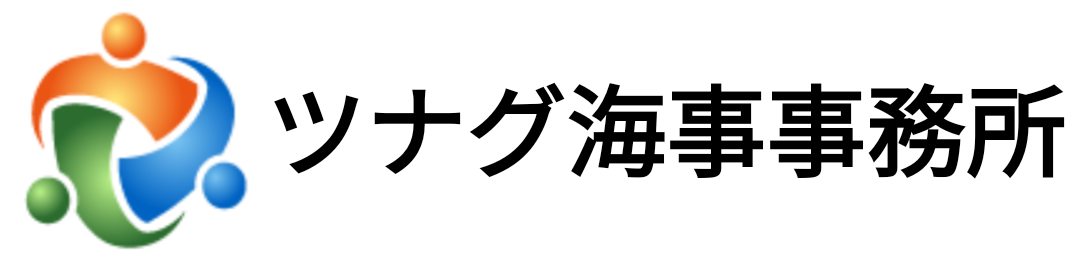マグロでも分かる船員法の解説⑧【年少船員・女子船員編】

船員法は、船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律であり、一般労働者で言うところの、労働基準法にあたる法律です。
船員労働には、長時間陸上から孤立し、「労働」と「生活」とが一致した24時間体制の就労があり、かつ、常に動揺にさらされる船内では、危険な作業をともなうなどの特殊性があることから、労働基準法とは異なる規律が必要です。そのため、船員には、厚生労働省が所管する労働基準法ではなく、国土交通省が所管する船員法が適用されます。
他方、一般社会において船員法を意識する機会はほとんどなく、改めてこれを検索しようにも、そもそも詳しく解説した文献はほとんど存在していません。
そこで当サイトでは、「マグロでも分かる海事法令」シリーズとして、「船員法」について深掘りした解説を行うことにしました。本編では、船員の「年少船員」と「女子船員」について解説しています。一般船員の取扱いとの違いについて意識しながらしっかりと確認するようにしてください。
★船員法の構成
- 第1章 – 総則
- 第2章 – 船長の職務及び権限
- 第3章 – 紀律
- 第4章 – 雇入契約等
- 第5章 – 給料その他の報酬
- 第6章 – 労働時間、休日及び定員
- 第7章 – 有給休暇
- 第8章 – 食料並びに安全及び衛生
- 第9章 – 年少船員
- 第9章の2 – 女子船員
- 第10章 – 災害補償
- 第11章 – 就業規則
- 第11章の2 – 船員の労働条件等の検査等
- 第11章の3 – 登録検査機関
- 第12章 – 監督
- 第13章 – 雑則
- 第14章 – 罰則
- 附則
目 次
年少船員
船舶所有者が成長途上にある年少者を過酷な船員労働に使用するにあたっては、その生命や健康を損なうことがないように、特段の配慮を行うことが求められます。
未成年者の行為能力
未成年者(18歳未満の者)が船員となるには、法定代理人の許可を受ける必要がありますが、法定代理人の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。
年少船員の就業制限
船舶所有者は、16歳未満の者(漁船にあっては、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く)を船員として使用することはできません。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この規定は適用されません。
また、以下の作業については、危険な船内作業又は船員の安全及び衛生上有害な作業として、18歳未満の船員をこれらの作業に従事させることはできません。
- 腐食性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
- 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装はく離の作業
- 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれを焚く作業
- 動力さび落とし機を使用する作業
- 炎天下において、直接日射をうけて長時間行う作業
- 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う作業
- 冷凍庫内において長時間行う作業
- 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
- タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗作業
- 塵埃(じんあい)又は粉末の飛散する場所において長時間行う作業
- 1人につき30kg以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
- アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業
船舶所有者は、18歳未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に18歳に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示して、国土交通大臣の認証を受ける必要があります。
年少船員の夜間労働の禁止
船舶所有者は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶を除き、18歳未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させることはできません。
ただし、船舶が高緯度の海域にあって昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合において午前0時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りではありません。
また、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事させる場合(海員にあっては、船長の命令によりその作業に従事する場合に限る)についても、この規定は適用されません。
女子船員
船員法には、労働基準法と同じく母性保護を図るための妊産婦に関する規定がありますが、船員法では、船員労務の特殊生を鑑(かんが)みて、労働基準法とは異なる措置が設けられています。
なお、女子船員に関するすべての規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については適用されません。
妊産婦について
船員法における妊産婦とは、労働基準法と同様に、妊娠中又は出産後1年以内の女子を指します。妊産婦については、妊娠中てあるか、産後どれくらい経過しているかによって、それぞれ異なる取扱いがなされています。
妊産婦の就業制限
船舶所有者は、原則として、妊娠中の女子を船内で使用することはできません。ただし、以下のいずれかの事由に該当する場合は、この限りではありません。
- 妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に2時間以内に入港することができる航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき
- 女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき
(※)妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があったときは、その者を軽易な作業に従事させる必要があります。
船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女子を船内で使用することはできません。ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りではありません。
また、以下の作業については、母性保護上有害な作業として、妊娠中又は出産後1年以内の女子(以下、妊産婦)をこれらの作業に従事させることはできません。
★妊娠中の女子の船員を従事させてはならない作業
- 揚錨機、ラインホーラー、ネットホーラーその他の錨鎖、索具、漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中の錨鎖、索具、漁具等の走行を人力で調整する作業
- クレーン、ウインチ、デリックその他の重量物を移動する機械又は装置を操作する作業
- フォークリフトの運転の作業
- 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業
- 切削又は穿孔用の工作機械を使用する作業
- 推進機関用の重油専焼罐に点火する作業
- 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業
- はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業
- 刃物を用いて鯨体を解体する作業
- 床面から2m以上の高所であって、墜落のおそれのある場所における作業
- げん外に身体の重心を移して行う作業
- 酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作業
- 石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、これらの物質を積載している船倉内で行う作業
- 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
- 腐食性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
- 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装はく離の作業
- 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれを焚く作業
- 動力さび落とし機を使用する作業
- 炎天下において、直接日射をうけて長時間行う作業
- 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う作業
- 冷凍庫内において長時間行う作業
- 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
- タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗作業
- 1人につき30kg以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
★出産後1年以内の女子の船員を従事させてはならない作業
- 揚錨機、ラインホーラー、ネットホーラーその他の錨鎖、索具、漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中の錨鎖、索具、漁具等の走行を人力で調整する作業
- クレーン、ウインチ、デリックその他の重量物を移動する機械又は装置を操作する作業
- フォークリフトの運転の作業
- 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業
- 切削又は穿孔用の工作機械を使用する作業
- 推進機関用の重油専焼罐に点火する作業
- 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業
- はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業
- 刃物を用いて鯨体を解体する作業
- げん外に身体の重心を移し
- 人体に有害な気体を検知する作業
- 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
- 腐食性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
- 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装はく離の作業
- 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれを焚く作業
- 動力さび落とし機を使用する作業
- 炎天下において、直接日射をうけて長時間行う作業
- 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う作業
- 冷凍庫内において長時間行う作業
- 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
- タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗作業
- 1人につき30kg以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
妊産婦以外の女子船員の就業制限
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員であっても、女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものとして定められている以下の作業に従事させることはできません。
- 人体に有害な気体を検知する作業
- 腐食性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
- 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剥離の作業
- 1人につき30kg以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
妊産婦の労働時間の特例
船員法の規定のうち、休日、時間外労働、補償休日の労働、休息時間の労働、労働時間の限度、労使協定による変形休息時間の付与、割増手当、労働時間の例外規定、休日の例外規定並びに定員の適用範囲等、特例等の規定は、妊産婦の船員については、適用されません。
船舶所有者は、妊産婦の船員を、1日当たり8時間以内という原則的な労働時間を超えて作業に従事させることはできません。ただし、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要がある場合において、この労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る)は、この労働時間の制限を超えて妊産婦の船員を作業に従事させることができます。
また、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の特別の必要がある場合において、労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る)は、下表の超過時間を限度とする作業に従事させることができます。
| 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき | 4時間 |
| 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき | 作業に従事するために必要な時間 |
| 航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき | 1時間 |
| 沿海区域を航行区域とする船舶であって国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶 | 4時間 |
| 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき | 2時間 |
労働時間の制限を超えて妊産婦の船員を作業に従事させる場合であっても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、労使協定の定めによる時間外労働の時間を含め、1日当たり14時間、1週間当たり72時間を限度とされています。
なお、妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、割増手当を支払う必要があります。
妊産婦の休息時間の特例
船舶所有者は、労使協定で定めるところにより、休息時間を、1日について3回以上に分割して、又は休息時間を1日について2回に分割して船員に与える場合において休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を6時間未満として、船員に与えることができます。
ただし、出産後8週間を経過した妊産婦の船員については、その休息時間を労使協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限りこれが認められます。
ただし、出産後8週間を経過した妊産婦の海員にあっては、以下のいずれかに該当する者に限り、この規定が適用されます。
- 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加する場合において作業に従事する海員
- 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が前二項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに乗り組む海員
妊産婦の休日の特例
船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間について少なくとも1日の休日(補償休日を除く)を与える必要があります。
たたし、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が以下の申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、妊産婦の船員を休日において作業に従事させることができます。
- 船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要がある場合において、休日において作業に従事することの申出
- 労使協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める日数を超えない範囲内で、休日において作業に従事することの申出
また、妊産婦の船員の労働時間が1週間において40時間を超える場合には、超過時間に対する補償休日を、その1週間に係る基準労働期間以内にその者に与える必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当するやむを得ない事由があるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができます。
- 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになったとき以降において航海の途中にあるとき
- 補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき
- 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき
- 補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき
なお、妊産婦の船員が休日において作業に従事した場合は、割増手当を支払う必要があります。
妊産婦の夜間労働の制限
船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させることはできません。ただし、船舶が高緯度の海域にあって昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合において、これと異なる時刻の間において午前0時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りではありません。
この規定は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事すること又は休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは適用されません。
生理日における就業制限
船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があったときは、その者を生理日において作業に従事させることはできません。
例外規定
船員法の規定のうち、労働時間、補償休日、補償休日手当、休息時間の原則、通常配置表、記録簿の備置き等並びに妊産婦の労働時間、休日の及び妊産婦の夜間労働の制限の特例の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事させる場合(海員にあっては、船長の命令によりその作業に従事する場合に限る)には適用されません。
まとめ
ただでさえ特殊な船員労務にあって、年少船員にせよ女子船員にせよ、何故法的保護が必要なのか、どのような措置が必要なのかを、一般船員に関する規定と比較しながら全章を通じて意識しながら学ぶようにしましょう。