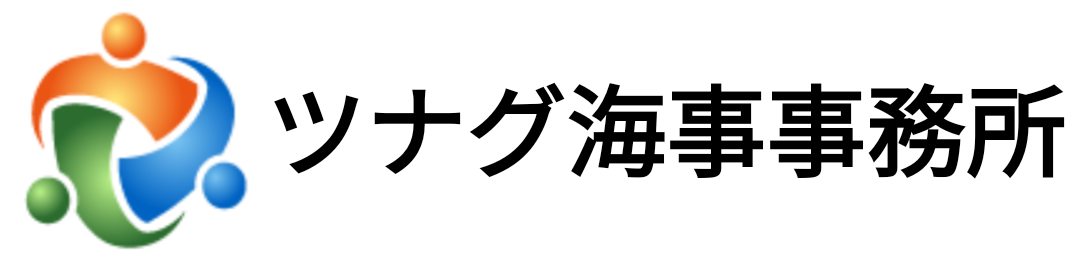船長最強説│こんなに面白い海事法令の世界

皆さまは「船長」と聞いて誰を思い浮かべますか?
最近なら麦わらさん?それともジャック・スパロウ?ひと昔前なら宇宙戦艦のO艦長あたりでしょうか?
海事代理士という職務上、一般の方よりも海事法令に触れる機会が遥かに多いわけですが、触れれば触れるほど、噛めば噛むほど、海事という極めてニッチな分野において、わざわざ海事代理士なる業務独占資格が存在している理由がよく分かるようになります。
端的に表現すれば「異彩」。
そこで今回は、皆さまが普段あまり接する機会のない海事緒法令の中から「船長」に関する規定を選りすぐり、解説とツッコミとを交えながら楽しくそして厳しくお届けしていきたいと思います。
海事法令の特殊性

ところで皆さまは「船員保険」をご存じでしょうか?今でこそ他の制度に組み込まれて統合されてしまいましたが、かつては何と年金保険、医療保険、労災保険及び失業保険のほぼすべての機能を網羅する社会保険制度のひとつでした。
旧船員保険制度は、昭和14年制定の船員保険法において、軍人並みの危険を伴う任務に就くことが想定される船員に見合う社会保障制度として導入されました。
また、現行の労働基準法においても船員について触れている以下の条文を確認することができます。
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
(労働基準法第116条)
このように現在でも労働基準法のほとんどの規定が船員に対しては適用されていません。これらの点を踏まえても、船員という職業がいかに特殊な環境下での労務であるかをうかがい知ることができるのではないかと思います。
船長の権限

船長とは言わずもがな船舶における最高責任者です。船舶の大小に関わらず船主から選任された最高責任者であればそれは船長です。そして船長はあくまでも民間人です。この点をまず最初にご確認していただいた上で、いよいよ船長の強大な権限の数々について触れさせていただこうと思います。(これは伏線です)
船長は、海員(乗組員)を指揮監督し、かつ船内にある者に対し、自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
(船員法第7条)
ふむふむ分かる分かる、、、ん?
いや、ちょっと待てよ?
船内にある者?
それってみんなってこと?
そう、つまりこの「船内にある者」には、海員はおろか旅客も船主も何なら総理大臣すらも含まれます。職務について必要であると判断すれば、客だろうが雇い主だろうがお偉いさんだろうが、お構いなく命令できてしまうのが船長です。
船長は、船内規律を守らない海員を懲戒することができる。
懲戒には上陸禁止と戒告の2種がある。
(船員法第22、23条)
上陸禁止!!体育会系!!
いやいや、体育会系を自称する私でもさすがに上陸禁止を命じられたことはありません。レベル1の戒告(いわゆる注意)との温度差よ。。
ちなみに海員らが守らなければいけない規律は以下の通りです。
1 上長の職務上の命令に従うこと
2 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと
3 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと
4 船長の許可なく船舶を去らないこと
5 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと
6 船内の食料又は淡水を濫費しないこと
7 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと
8 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと
9 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと
10 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと
(船員法第21条)
校則ですか?(いいえ法律です!)
先輩や監督が絶対だった学生時代を思い出します。個人的には朝練でこんな感じの声出しをしていたような思い出があります。
船長は、海員が船内にある者の生命、身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、これらの処置をすることができる。
(船員法第26、27条)
妥当であるように思われますが、「必要な処置」の範囲が気になるところです。ちなみに「必要な処置」をとる対象をわざわざ「旅客その他船内にある者」にまで広げているため、旅客も船主もインフルエンサーも大御所芸人も皆さん処置とられ対象です。あ、船長は民間人です。警察ではありません。あしからず。
船長は、海員が雇入契約の終了の届出をした後も船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶を去らせることができる。
(船員法第28条)
令和のご時世にあって、強制退去が認められている職業ってなかなかありませんよね?
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、船内における犯罪につき、司法警察員として、犯罪の捜査、犯人の逮捕などの行為を行う。
(司法警察職員等指定応急措置法など)
再度確認しますが船長は民間人。遂に警察と同等の権限が与えられました。コナン君も船長だったら合法的に捜査できますね!(まぁ小学生は船長になれませんけども。)
さらにはこんな事まで…
船長は航海を継続するため必要なときは積荷を航海の用に供することができる。
(商法第712条)
積み荷である食糧や燃料については航海の継続のために必要であれば船長判断により使用することが可能です。所有者が誰であるかなんか関係ない!
船長は、船舶の航行中、船内にある者が死亡したときは、国土交通省の定めるところにより、これを水葬に付すことができる。
(船員法第15条)
こんなシーン映画でしか見たことありません。願わくばそうなりたくないですけども。
航海中に出生又は死亡があったときは、船長は戸籍吏の職務を担当する。
(戸籍法第55条)
戸籍吏とは戸籍を扱う旧制度上のお役人の名称です。現代風に言い換えれば要するに市町村長のことを指します。
遂に首長のポジションにまで!!
そういえば行政書士試験の勉強中、民法にもこんな条文があったことを思い出しました。
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(民法978条)
うーん。やっぱり船長は偉大なり!!
船長の義務

さて、ここまで船長の強大な権限について語って参りましたが、当然ながら船長にはその権限以上に重い義務が課されています。
- 発航前の検査
- 航海の成就
- 甲板上の指揮
- 在船義務
- 航海当直の実施
- 巡視制度
- 旅客に対する避難の要領等の周知
- 船舶に危険がある場合における処置
- 船舶が衝突した場合における処置
- 遭難船舶等の救助
- 異常気象などの通報
- 非常配置表の作成及び操練
- 航海の安全の確保
- 遺留品の処置
- 在外国民の送還
- 船員法上の書類備置義務
おもな船長の義務は上記のとおりですが、これら以上に有名なものが「最後離船義務」と言われる以下の規定ではないかと思います。
船長は船舶に急迫した危険があるとき、人命、船舶および積荷の救助に必要な手段をつくし、かつ、旅客、海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ、自己の指揮する船舶を去ってはならない。
(旧船舶法第12条)
船長の最後離船義務については都市伝説的に語られてきましたが、これは法律に明記されていた紛れもない事実です。
ただし、現在この規定はさすがに改正されており、現行の船員法上では次のようなマイルドな表現に置き換えられています。
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段をつくさなければならない。
(船員法第12条)
とは言え「手段をつくさなければならない」ことには違いないので、最後離船とまではいかなくとも、船長がすべての乗船員中で最も重い責任を負う立場であることは間違いありません。
キャプテン、お疲れさまです!!
まとめ

ここまでご覧になられて海事法令の特殊性を少しはご理解いただけたのではないかと思います。一見して令和の時代にはそぐわないようにも感じますが、船舶が陸から切り離されたひとつの自治体であるととらえ、船長はその首長であるものとすると理解が深まるように思います。海上は常に危険と隣り合わせの環境ですから、緊張感を維持するためにはこのような厳格な規律が必要なのかもしれません。
その一方で、昔ながらのスタイルを貫く海事法令には、社会情勢とともに変化する陸上の法令との対比に面白みを見出すという楽しみもあります。普段馴染みの浅い海にまつわる様々な情報を発信することで、海や海事代理士についてもっと興味を持っていただけるようになれば幸いです。